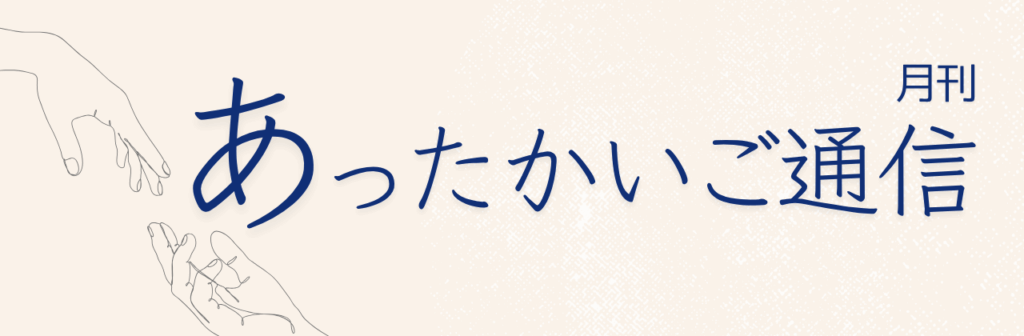
近年、障がい者グループホーム(GH)の事業所数は全国的に増加傾向にあります。
なかでも、重度障がい者の生活を支える「日中サービス支援型グループホーム」の伸びが特に顕著です。
この拡大の背景には、以下のような要因が挙げられます。
重度の障がい者を受け入れる地域資源が不足している
営利法人の参入が増加し、事業所数が拡大している
ただし、この急速な増加に対しては、現場からもさまざまな課題の声が上がっています。
施設数が増加する一方で、有識者からはサービスの質の低下を懸念する声も聞かれています。
「本当に支援が必要な重度障がい者が利用しにくくなっているのではないか」
「運営主体によって、サービスの質に差があるのではないか」
これらの声に対して、厚生労働省は現在策定中のガイドラインに基づく運営ルールの整備を進めており、サービスの質向上に向けた対応を表明しています。
一方で、現場の一部からは、
「サービスの質や入居対象者の選別は、営利法人であればある程度やむを得ない」
という意見もあり、制度と現場の間にある温度差も浮き彫りになっています。
就労継続支援A型事業所についても、注目すべき変化が起きています。
営利法人主体の割合は増えている一方で、2024年12月時点の総事業所数は4,384カ所となり、
報酬改定前(2024年3月)から250カ所の減少が確認されました。
この減少の要因としては、報酬制度におけるマイナス評価の導入などが挙げられています。
問題は、こうした事業所の閉鎖により、そこを利用していた障がい者の新たな受け入れ先が不足している現状です。
今後は、グループホームの質の向上と、安定した受け入れ体制の両立がより一層求められています。
介護・福祉業界においては、深刻な人材不足が続いています。
その解決策のひとつが、特定技能などの外国人職員の採用ですが、
採用後には「住まいの確保」という課題が発生します。
実際、外国人という理由だけで賃貸住宅の契約が難航するケースが少なくありません。
この問題に対して、ある法人では以下のような取り組みが実施されています:
施設長が地域の自治会長を兼任し、「顔の見える関係」を構築
地域住民と外国人職員との日常的な接点を設け、トラブル回避や理解促進に貢献
介護事業者が主体となって、外国人職員向けの住まいを確保する取り組みが今後ますます重要になります。
たとえば:
外国人職員の増加を見越し、法人が土地を取得して職員寮を新築または改修
その中に、地域住民と交流できるスペースや、共生型デイサービスを併設
地域の高齢者や障がい者、外国人職員が一体となる暮らしの場をつくる
このような仕組みは、地域の理解醸成と人材の定着を同時に進める施策として、今後注目されていくでしょう。
弊社では、介護・障がい福祉施設の建築支援に加え、運営や人材活用に関するコンサルティングまで幅広く対応しております。
重度障がい者グループホームの設計・建築
外国人職員を見据えた寮併設型施設の開発
調整区域や土地活用に関する許認可サポート
安定経営のための収支計画・補助金活用アドバイス
弊社では、福祉施設の新規開設から運営支援までトータルでサポートしています。
施設づくり・人材育成・制度活用など、介護・福祉事業のパートナーとしてお役立ていただけます。